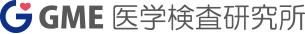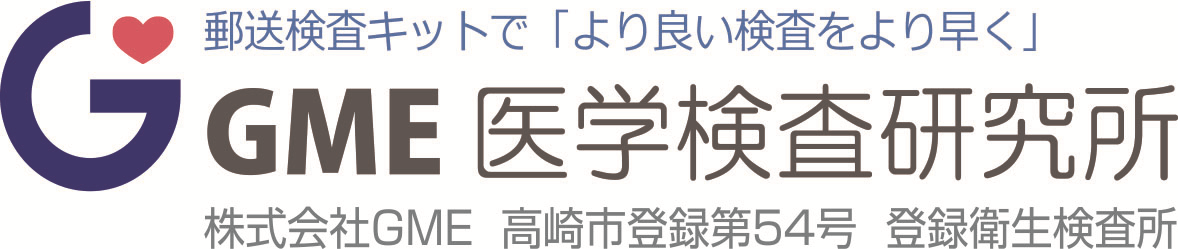非クラミジア性非淋菌性尿道炎とは?
症状や検査方法、予防、治療法について
症状や検査方法、予防、治療法について
非クラミジア性非淋菌性尿道炎とは
非クラミジア性非淋菌性尿道炎(ひくらみじあせいひりんきんせいにょうどうえん)とは、淋菌またはクラミジアが原因ではなく、それ以外の病原菌が原因で起こる尿道炎をいいます。
非クラミジア性非淋菌性尿道炎の原因菌としてはマイコプラズマやウレアプラズマなどが注目されていますが、現状では病原菌を特定できない非クラミジア性非淋菌性尿道炎もあります。
性感染症の一つである男子尿道炎は、
・淋菌性尿道炎(gonococcal urethritis,GU)
・非淋菌性尿道炎(non-gonococcal urethritis,NGU)
とに分けられます。
非淋菌性尿道炎は男子尿道炎の約70%を占めます。
非淋菌性尿道炎(NGU)患者のうち尿道擦過物あるいは初尿からクラミジアが検出されるのは、30~40%にすぎず、その残りは、淋菌やクラミジア以外の他の病原菌が原因となっています。
非クラミジア性非淋菌性尿道炎の原因菌としてはマイコプラズマやウレアプラズマなどが注目されていますが、現状では病原菌を特定できない非クラミジア性非淋菌性尿道炎もあります。
性感染症の一つである男子尿道炎は、
・淋菌性尿道炎(gonococcal urethritis,GU)
・非淋菌性尿道炎(non-gonococcal urethritis,NGU)
とに分けられます。
非淋菌性尿道炎は男子尿道炎の約70%を占めます。
非淋菌性尿道炎(NGU)患者のうち尿道擦過物あるいは初尿からクラミジアが検出されるのは、30~40%にすぎず、その残りは、淋菌やクラミジア以外の他の病原菌が原因となっています。
原因
非クラミジア性非淋菌性尿道炎の病原菌の候補として各種の病原体による非淋菌性尿道炎の可能性が検討されてきました。
その中で、マイコプラズマとウレアプラズマが非淋菌性尿道炎と関連があることが示唆されるようになってきたものの、マイコプラズマやウレアプラズマも検出されない非クラミジア性非淋菌性尿道炎に関しては、今なお、その病因は不明です。
その中で、マイコプラズマとウレアプラズマが非淋菌性尿道炎と関連があることが示唆されるようになってきたものの、マイコプラズマやウレアプラズマも検出されない非クラミジア性非淋菌性尿道炎に関しては、今なお、その病因は不明です。
主な原因

性的接触
性交渉・オーラルセックスなど
性交渉・オーラルセックスなど
症状と潜伏期間
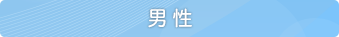
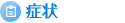
- 尿道からの分泌物
- 排尿時の痛み
- 尿道の掻痒感(かゆみ)
*淋菌による尿道炎と比べて症状は軽度の場合が多いです。
*クラミジアによる尿道炎とは、症状が似ていて、大きな差が認められません。
*マイコプラズマあるいはウレアプラズマが原因となる尿道炎の場合でも、特徴的な症状は認められません。

- 1~5週間
検査について
◎検査を受けられる機関
● 病院・医療機関(泌尿器科・性病科)

◎検査
男性尿道炎の診断は、症状と、尿道分泌物中の多核白血球の有無、そして尿道分泌物のグラム染色標本の所見により行われます。
尿道分泌物中にグラム陰性双球菌を認めた場合には淋菌性尿道炎とし、認められない場合には非淋菌性尿道炎として診断し、治療を開始します。
病原菌について初診時に淋菌およびクラミジアの検査を行いますが、マイコプラズマやウレアプラズマなどの微生物の検出は、通常では行われていません。
尿道分泌物中にグラム陰性双球菌を認めた場合には淋菌性尿道炎とし、認められない場合には非淋菌性尿道炎として診断し、治療を開始します。
病原菌について初診時に淋菌およびクラミジアの検査を行いますが、マイコプラズマやウレアプラズマなどの微生物の検出は、通常では行われていません。
予防
非クラミジア性非淋菌性尿道炎は、すべての原因が性交渉というわけではありません。
身体の免疫力が低下しているときなど、様々な理由で細菌が尿道に入ってきた場合、尿道炎を引き起こす可能性があります。
身体の免疫力が低下しているときなど、様々な理由で細菌が尿道に入ってきた場合、尿道炎を引き起こす可能性があります。
性的感染からの予防
性行為の際は、最初から最後まで、コンドームを正しく使用する。
その他の予防
・性器を清潔に保ち、尿道に雑菌が入らないようにする。
・不特定多数の人との性的接触を避けるようにする。
・不特定多数の人との性的接触を避けるようにする。

治療法
● 抗菌薬の服用(テトラサイクリン系、マクロライド系あるいはニューキノロン系など)
通常非クラミジア性非淋菌性尿道炎の症例に対しては、クラミジアに抗菌活性のある抗菌薬を服用します。抗菌薬の服用により、クラミジアによる尿道炎だけでなく、非クラミジア性非淋菌性尿道炎の大多数の症例においても自覚症状と炎症所見の改善が認められます。
治癒判定:自覚症状の改善と、尿道分泌物または初尿沈渣中の多角白血球の消失が確認できれば、治癒となります。
パートナーに何らかの症状がある場合には、同時に治療することが必要です。